
“気仙沼で子どもたちがバスケットボールができる”ということを皆さんはどう感じますか?
「そんなの当たり前だよ」と感じる方がほとんどなのではないでしょうか。
しかし、震災前の気仙沼には小・中学生を対象としたバスケットのスポーツ少年団はなく、ミニバスケットチームもほとんどなかったんです。
そこから現在は、スポーツ少年団や小学生対象のミニバスケットチームはもちろん、中学生対象のバスケットスクールまでが設立し、気仙沼のバスケット環境が整っているのがわかります。
また、“気仙沼フカヒレCUP”や“島バス”といった、気仙沼の観光資源を生かしたバスケットの大会も行われています。そんな気仙沼のバスケット環境をつくりあげた一人が、袖野洸良さんです。
袖野さんは少年団の監督やスクールのコーチを務めながら、気仙沼市バスケットボール協会員として気仙沼で行われるバスケット行事の企画運営を行っています。
そんな、バスケットの指導から環境づくりまで幅広く行う袖野さんから、気仙沼の子どもたちにバスケットが根付くまでのお話とともに、子どもたちにバスケットの機会をつくり続ける理由をうかがいました。
[text&photo:平田和佳]
バスケットで気仙沼を元気に

(写真提供:袖野洸良)
元々小学生の頃は野球をやってたんですが、試合でデッドボールを食らった時に、本当に痛くて。それでもう野球はやらないって思って。
そこから、父がバスケットをしていた影響もあり、中学ではバスケットをやりはじめました。バスケを始めてみると、周りと比べて自分は下手くそで。始めたばかりの時はサボり気味でしたね。
バスケットに燃える今の袖野さんからは全く想像できないバスケットとの出会い。
しかし、練習するたびに少しずつ上達できる楽しさを感じて、バスケットにのめり込んでいったそうです。そこから大学でもバスケを続けていた袖野さんは、大学1年の時に怪我をしたことから選手の道ではなく、指導者としての道を歩み出します。
教員免許も取得し、指導者として最初に赴任したのは「登米高校女子バスケットボール部」。過去に県大会優勝経験もある古豪ということで、“試合に勝つための指導”に心血を注いでいました。

そんな登米高校での指導が3年目の年である、2011年に東日本大震災が気仙沼を襲いました。
変わり果てた気仙沼を目の当たりにしながら、自分の大好きなバスケットを見つめ直したそうです。
今までは、自分が好きだから、楽しいからという理由でバスケットをしてたんです。
でも、被災した気仙沼を見て、自分が楽しむだけではなく、バスケットで気仙沼を元気にしたいと思うようになりました。
楽しさを感じられる環境づくり

2021年のスポーツ少年団の様子(写真提供:袖野洸良)
子どもたちへの環境づくりと並行しながら、ミニバスケットや少年団での指導も行っていたころ、ミニバスケットではどんどん上達していく子どもたちと裏腹に、だんだんと新しく入団してくれる人が少なくなっていました。
今までは、バスケットを経験してきた高校生を対象にした指導で、どうやったら強くなるか、ということを大事にしてきました。だから、教えることは“やって当たり前”、“頑張るのも当たり前”だと思ってました。
でも、ミニバスケットで教える子どもたちは未経験の小学生なんですよね。
だから、「今までの指導法で指導していた子どもたちは、やってて楽しくなかったのかな?」と考えるようになり、自分の指導法を見直しはじめました。
そこで、やっぱり、スポーツを続ける意味は“楽しさ”であり、自分の指導はもっと子どもたちが“楽しさを感じれるもの”にしていかないと、と思いました。
そうと気づけば、すぐに行動に移していくのが袖野さん。
ゲーム的要素を入れたメニューを用意して練習にメリハリをつけてみたり、「しつもんメンタルトレーニング」 や「アンガーマネジメント」の資格を取って子どもたちとの関わり方を見直したりと、指導法から自分のあり方まで、できることは全て改善していきます。
また、子どもたちの指導法をスタッフ全員が共通理解できているか話し合ったり、男女や習熟度で分けて適切な指導ができるようにしたりと環境自体もより一層整えていきました。

今では、未就学児が対象の「ちびバス」、小学生対象の「スポーツ少年団」、スキルアップを目指したり、部活にバスケットがなかった中学生も参加できる「バスケットスクール」と、子どもたちがどんな年代からでもバスケットに触れられるような体制ができました。
そして、どの団体であっても、子どもたちにあった指導ができるように、スタッフたちみんなで頑張っています。また、有難いことに、活動に対して保護者の皆様からのバックアップもいただけてることで、より良い環境がつくられていると感じています。
バスケットを生涯スポーツにしたい

2019年のフカヒレCUPの様子(写真提供:袖野洸良)
袖野さんは子どもたちへの環境づくりはもちろん、社会人向けのバスケットクラブやリーグの運営、そして大会の開催にも尽力されています。
そして大会は、体育館ではなく、レンタルコートを用いて屋外にコートを設置して、まちなかで大会を行うことで、試合の合間に気仙沼の食や土地柄に触れられる仕立てにしてみたりと、ひと味違うのも特徴的です。
大会は気仙沼市外から選手が訪れてくれます。そんな選手が試合だけではなく、気仙沼自体も楽しんでくれること。そして、その試合がたまたま通りがかったまちの人たちの目にも触れることで、バスケットがより身近なものになったらと考えています。
おかげで、「今度はここでやってほしい」とお話をいただくようにもなりました。

スポーツリズムトレーニングの指導の様子(写真提供:袖野洸良)
バスケットの土壌がつくられ、機運が高まるなか、袖野さんは大きく舵をきります。
「一般社団法人スポーツLABO」の設立です。
僕はバスケットを生涯スポーツにしたいんです。
コンタクトスポーツで激しいイメージから、生涯スポーツとはかけ離れているようにも思いますが、バスケットを少しでも長く楽しめるようにしていきたいと思っています。だから、小さい子はもちろん、お年寄りの方の体づくりもお手伝いできればと考えています。
「スポーツLABO」では、子どもだけにとどまらず、大人から高齢者にも対象を広げています。そして、運動環境・習慣を広げたいという思いから、音楽のリズムに合わせながら楽しく体を動かせる“スポーツリズムトレーニング”の普及に力を入れています。
なんと、袖野さんはバスケットを始める前の土壌づくりから行おうとしているんです。一体どこまで、袖野さんはバスケットの環境を整えていくんだろう、と感嘆していたのもつかの間、
今、少し考えているのは、40代から50代を対象にしたリーグづくりなんですよね。
と続けます。
土壌づくりだけにとどまらず、また新しくバスケットの機会を作ろうしている袖野さんはなんだか楽しそうでした。

自分は思いついたことをやってるだけなんですよね。
その思いつきを一緒にやってくれる仲間がいるからできてることばかりですよ。
と、袖野さんは軽やかに話します。
何もなかったところから、こんなにも多くの場所をつくり出してきた10年。きっと袖野さんはバスケットが生涯スポーツとして楽しめる気仙沼を実現していくんだろうな、と思わずにはいられません。
そして、袖野さんがいれば、「バスケットを誰でも思いっきり楽しめるまちといえば、気仙沼だよ」と自信を持ってご紹介できそうです。
市外にお住いの皆様は、まずは大会からご参加ください。
きっと、どこよりも楽しく、そして気仙沼を感じながらバスケットができるはずです。
■人物紹介
袖野洸良(そでのみつよし)さん
スポーツリズムトレーニング協会認定インストラクター、メンタル心理カウンセラー、日本バスケットボール協会B級コーチ、宮城県バスケットボール協会理事など、様々な資格を持ちながら、バスケットに携わる。
——————————
誰もがバスケットを楽しめるまちにしたいと話す袖野さん。教員時代に、支援学校に勤めていたことで、より一層一人ひとりの特性を把握して理解するようになったそうです。また、リズムトレーニングで高齢者の方と接する機会が増えたそうですが、実は介護の仕事をやっていた経験も活きているそう。一体どこまで関わる人が増えていくのか…!

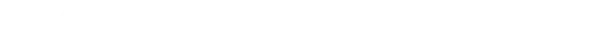
最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。