
みなさん、こんにちは!私は気仙沼にある「リアス・アーク美術館」で学芸員をしている、萱岡雅光です。
これまで、気仙沼の歴史や文化について記事を書いてきました。
過去の記事についてはこちらからご覧ください。
今回のテーマは……
気仙沼がロケ地となった映画『サンセット・サンライズ』。2025年7月、DVDが発売されました。劇中には当地域の方言や食べ物がこれでもか、というほど登場しましたが、特に印象的だったのが、「け」。これは「食べなさい」という意味で、地元の人に食べ物を渡されつつこの言葉を投げかけられた主人公(菅田将暉さん)が戸惑うシーンがありました。そこで今回は、気仙沼の美味しい食べ物を「け!」というメッセージを込め、映画に登場したものを中心に、気仙沼の食文化について解説します。映画を観た人も、観ていない人も、読めばきっと食べたくなるはず!?
(1)どんな食べ物?
最初に紹介するのは「あざら」。あざらは白菜の古漬けをメヌケのアラや味噌等と一緒に酒粕で煮る料理……。大体はこのように説明されます。しかしこれだと「結局どういうこと?」という方も多いと思いますので、当記事ではもう少し踏み込んで説明します。「メヌケ」とは深海に生息する赤い色をしたメバル属の総称で、あざらにはバラメヌケやオオサガ等のアラを使いました。白菜の古漬けとは、発酵が進み酸味がでてきた白菜の漬物。これらを酒粕と一緒に、コトコトと煮るのです。酒粕で魚を煮る料理は各地にありますが、既に発酵している完成品の漬物と魚のアラを一緒に煮る料理は珍しいです。漬物の酸味、魚の旨味と脂、酒粕の香り…。これらが見事に調和した、濃厚かつ複雑な味わいです。
(2)有名だけど謎も多い
気仙沼の「郷土料理」として真っ先に挙げられるあざらですが、有名な割には謎が多い料理です。例えば「あざら」という名称の由来。仏僧の名前に由来する等、諸説ありますが、個人的にはどれもピンときません笑。いつ頃から食べられていたのかについてもはっきりしませんが、これは材料からある程度推測できます。白菜は中国から移入した新しい野菜ですが、国内での育成・採種技術が確立し、庶民の食卓にまで浸透したのは大正~昭和初期だとされています。白菜漬けを用いたあざらは、これ以降に生まれたものと思われます。
(3)生業と工夫の結晶
あざらは各家庭で作られてきた料理ですが、作られる時期は、白菜漬けが古漬けとなる春先です。メヌケ漁は夏期のカツオ漁と組み合わせる形で、冬から春にかけて盛んに行われ、この時期に多くの水揚げがありました。なおこのメヌケ延縄漁の技術が後に「遠洋マグロ延縄漁のまち」の基礎となった節があるのですが、それはまた別の機会に。そしてもう一つ、酒粕は日本酒醸造の過程で生まれる副産物ですが、気仙沼には老舗の作り酒屋があり、日本酒を作る冬から春先にかけて、一般家庭でも酒粕の入手が容易でした。以上の条件が組み合わさり、あざらという奇跡の料理が誕生したのです。魚のアラ、古くなった漬物、酒粕を組合せたのがあざらですが、どの材料のチョイスにも根底に、食べ物を無駄にしない精神性があります。-を掛け合わせ、見事に+に転化した先人の工夫こそ、この料理の本質と言えるでしょう。
(1)どんな食べ物?
モウカはネズミザメのこと、ホシは心臓を表す言葉です。つまりモウカのホシは、ネズミサメの心臓のお刺身ですね。ごま油や酢味噌をつけて食べます。見た目に反して生臭くなく、食べた感じは「レバ刺し」にかなり近いです。モウカのホシは鮮度が命!新鮮なモウカのホシは、「サメのまち」気仙沼の誇りです。
(2)歴史や食べられる飲食店など
こちらの記事で詳細に解説されているので、ご参照ください。素晴らしい記事です!

(3)ホシを食べる
ホシ料理は他にもあります。代表的なものはカツオのホシ。串焼きや醤油・味噌などで煮ます。
(1)どんな食べ物?
メカジキの背ビレの付け根部分。付け根と、ヒレ筋の間に肉があり、食べ応え抜群。煮付けや塩焼きにして食べます。菅田将暉さんが気仙沼でのロケ中に食べてその美味しさに驚いた、ということで話題になりましたね。
(2)由来と歴史
「ハーモニカ」の由来は、筋が柵状に並ぶ見た目が楽器のハーモニカに似ているから、あるいは、かぶりついた時にまるでハーモニカを吹いているように見えることから、等の説があります。個人的には見た目だと「鍵盤ハーモニカ」の方が似ている気がしています。
(3)気仙沼とメカジキ
気仙沼が水揚げ量日本一を誇るメカジキ。突きん棒漁や延縄漁、大目流し網漁などで獲られます。突きん棒漁は千葉や大分で古くから盛んでした。大正期には房総の漁師が北上するメカジキを追って三陸沿岸に出漁し、大槌などで突きん棒漁の技術指導を行っていました。気仙沼では遅くとも昭和前期には突きん棒によるメカジキ漁が行われていました。戦後、マグロ延縄漁の隆盛に伴い、混獲により漁獲量も増えました。現在では高級なイメージのあるメカジキですが、地元の人に話を聞くと、昔はむしろ安い魚のイメージが強かったとのこと。昔は肉が高かったので、カレーにメカジキの肉を入れて食べていたそうです。現在では「メカカレー」として名物化され、市内各飲食店で提供されています。他にも「メカしゃぶ」など、新メニューの開発が積極的に試みられています。
どんな食べ物?
ドンコ(チゴダラ)を使った味噌汁です。具はドンコの身と肝、大根、豆腐など。どんこ汁は肝がキモ!ドンコの身は柔らかくてほっこり、汁は肝で濃厚。独特な香りと味わいは例えるなら豚汁が近いでしょうか。どんこ汁は「冬の季語」。どんこ汁を食べると今年も冬が来たなぁ、と感じる家庭の味です。映画でも、お店のメニューではなく家庭料理として登場していました。
恵比寿様に供える魚
どんこ汁が食べられる日と言えば、旧暦10月20日(新暦だと12月上旬頃)の「恵比寿講」。この日は、恵比寿様を祀る日で、大漁、商売繫盛を祈り、供物として神棚にドンコを供えてからドンコ汁にして家族で食べる風習があります。恵比寿様と家族が一緒に食べる神聖な食べ物でもあったわけですね。
(1)オクズガケ
クズでとろみをつけた汁物です。具は野菜や麩などで、お彼岸やお盆の時に食べられる精進料理です。具や味付けはお正月のお雑煮と同じく、家や地域で千差万別。野菜の出汁が出て、優しい味わいです。個人的にはシイタケが入っていたら、テンションが上がります。
(2)ほうろぎばっと
こちらは映画に登場していませんが、オクズガケと一緒にお盆に食べられることが多いです。いわゆる「はっと」の一種で、小麦粉を水で捏ね、三角形に切ったものに、砂糖と黄粉をたっぷりかけて食べます。ほうろぎとは方言の「ほろぐ」で意味は落とす、つまり余分な黄粉を払い落す、あるいは逆にはっとに黄粉を放るようにまぶす様子に由来するとされます。8月16日の送り盆の朝に食べる家が多く、気仙沼を離れた人にとっては帰省の味と言えるかもしれません。素朴で飽きのこない上品な味です。
おわりに
また長くなってしまいました……。最初は15種類くらいの食べ物を紹介するつもりでしたが、あざらの説明を書いている途中で「これ無理だわ」と悟り、全てを紹介することを断念。結局半分も紹介できませんでした泣。というわけで、気仙沼の食文化についてまた別の記事で引き続き紹介しようと思います。本記事の中で気になる食べ物がある、という方はぜひ気仙沼に「こ(来て)!」そして「け(食べて)!」
それではまた次回の記事でお会いしましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました


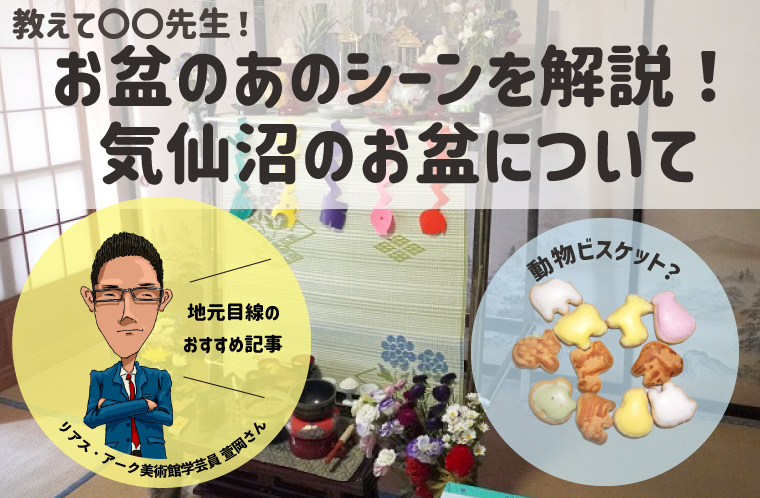

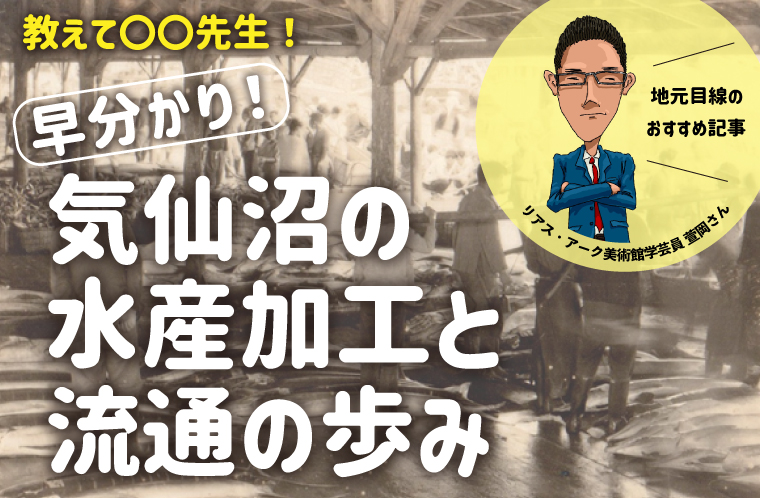
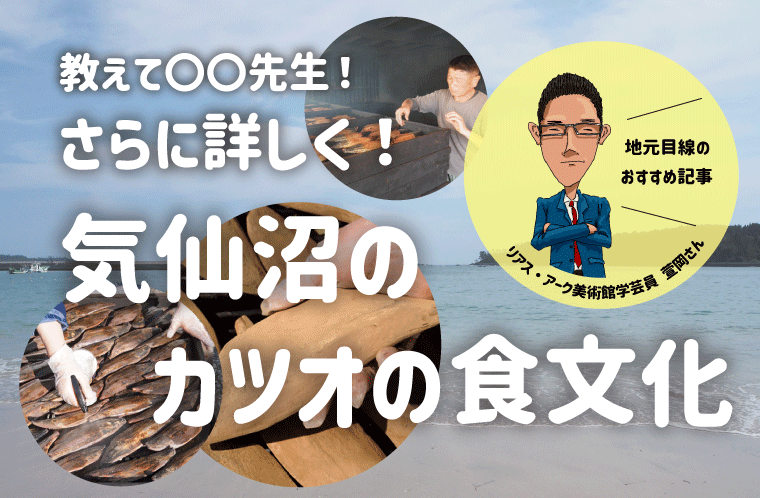
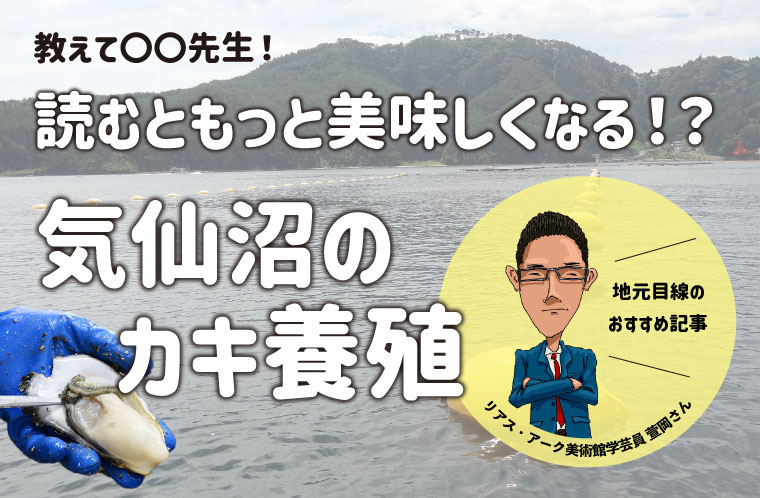
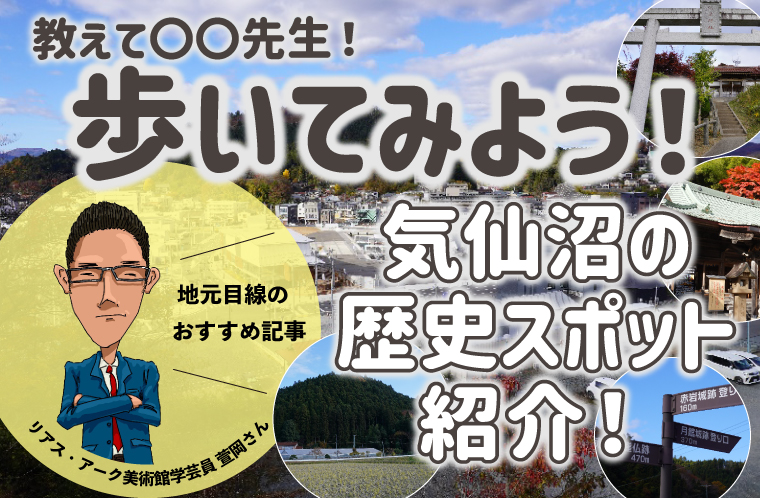
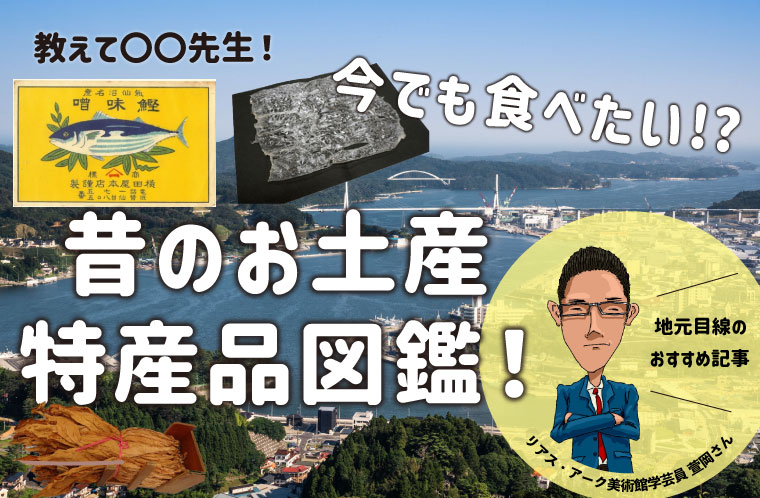




















最新の情報については各問い合わせ先にお問い合わせください。