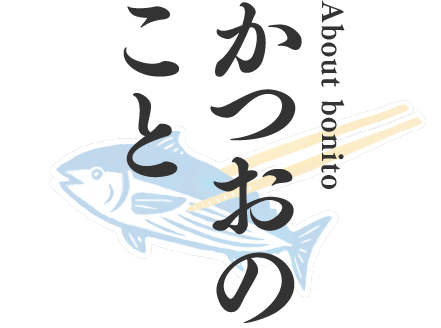和歌山から伝来したかつお溜め釣り漁
1675年(延宝3年)に、当時の紀州の三輪崎(現・和歌山県新宮市)の人たちが船で唐桑村鮪立(現・気仙沼市唐桑町鮪立)を訪れ、カツオを大量に漁獲するための新しい漁法「溜め釣り漁」を伝授したのが始まりとされています。この「溜め釣り漁」は、生餌をまいて魚を集めて漁をする、現在の一本釣り漁につながる漁法であり、大量にカツオを漁獲する方法として、カツオ漁を飛躍的に発展させたとされています。これをきっかけに市内でのカツオ漁が盛んとなり、現在の水産都市気仙沼を作る一つの基盤となりました。
海でつながる和歌山と気仙沼
気仙沼市と和歌山県のつながりは深く、奈良時代の718年までさかのぼります。奈良朝廷が全国統治を目指して東北へ攻め入っていたこの時期、朝廷軍は蝦夷討伐を祈願して霊験あらたかな熊野神社から御神霊を勧請し、室根神社に祀りました。この際に用いられたのが、現在の和歌山県新宮市から気仙沼市をつなぐ海路であり、気仙沼市の唐桑町鮪立の港に降り立った一行は、陸路で室根山を目指したそうです。この海路が、その後のかつお溜め釣り漁伝来にもつながっていきます。